企業の中において、、、
本当は流行りでやるものじゃないし、時代も関係ない。
いつだってそうであって欲しいもの。
僕はそう思う。
「時代」で言えば、どちらかと言えば「チャンスを逃してしまった時代」と言えるし、「手段の目的化」が進んでしまっている時代かもしれない。
ちまたでよくいわれる女性の活用、残業抑制、マイノリティや人種・宗教など、それらのことは手段であって目的ではない。その他の様々な要素もそう。

創業者やリーダーたちの経験や哲学の中から、D&I的な要素をその情とともに伝えられれば、そこには感動が起こりやる気やその気を拡大させられたかもしれない。
でも、もういまとなっては、「そういう時代だから」、「みんなやってるし」と、本当はそこに哲学も情もあったかもしれなくても、それはもはや伝わらない。日本語には「理動」という言葉はない。人間は感じて動くものであって、理屈で動くものではない、というひとつの証拠だと思ってる。
D&I が企業における「競争力」と関連づけて語られることは好きではない。
なぜだろうと考えると、多くの企業が理念として掲げている、「地域社会への貢献」。
言い回しは違えど、ほぼ同義の理念を掲げている企業が多いなか、そんな企業が他社を負かして1番となることと、その理念との兼ね合いってどういうことになるのだろう。
「社会」って? 企業がいう社会の範囲って? 他社は社会には入らないのだろうか?
企業の活動における”問い”ってなんなのだろう・・・
自分がひとつ思うことは、単純に「良い会社」を目指せばよいのではないかと思っている。
それは、他人がどうこうという他人軸ではなく、あくまで自分の中での軸を持つという、自分軸を大切にすることだと思う。
そういったことを考えたとき、ダイバーシティ & インクルージョン の目指すところは、競争力やNo.1になるため、ということではなく「レジリエンス※」なのだと思っている。もう少し単純に自分の言葉で言うと「変化に強い」ということ。

企業として内部環境、外部環境のあらゆる変化にも適応できる力をつけ、活動を継続すること。
松下幸之助は経営の大切さについて「自然の摂理に従うこと」と確か言っていた。その言葉に習って考えてみても、生物が絶滅を逃れるための手段としては、単一でいるよりも、多様である事の方がそれを逃れる可能性が高くなる。
企業活動においても同様のことが言えるのではないか。
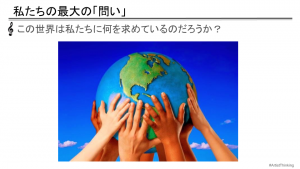
企業活動の本音である「自分の財布を厚くする活動」とまだまだ綺麗事から脱出できない「社会貢献」との乖離や本質を追求しない限り、本物のD&Iはいつまでたっても実現されないだろうと思う。
「そもそも論」がどこまでできる組織なのか、アクティブリスニング力、破壊を伴う本物の創造。そしてそれらを実現するために必ず必要なのが「信頼」です。
